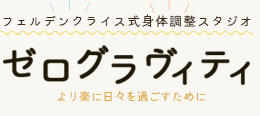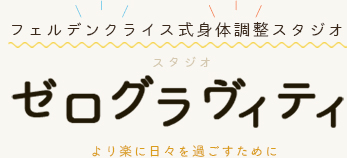『アレクサンダー・テクニック
の使い方』 

この本を書店で見つけたとき、何よりも目次に目を惹かれた。
それは、
隠蔽された見知らぬ「わたし」
「ずれることができる」という「能力」
「できてしまう」ということの「罠」
「しようとする」のではなく「しなくてよい」ことを「しない」
「固定」と「安定」、この似て非なるもの
「効果があった」という新たな「のろい」
などの小見出しである。
これらの言葉でいろいろなイメージが喚起され、野口体操のあれこれやフェルデンクライスメソッドのあれこれが思い出され、棚に戻せなくなってしまった。
著者は、日本人のアレクサンダー教師の草分けのひとりで、京都を拠点にして活躍されている。
今では、Googleのような検索サイトから「アレクサンダー・テクニック」を検索すると、3000以上のページにヒットするが、4~5年前には数件しかヒットしなかった。著者のホームページ(http://atcstudiok.la.coocan.jp/)はその頃からすでにあった。
本書では、hands-on(ハンズオン)、mapping(マッピング)、direction(ディレクション)、primary control(プライマリー・コントロール)といったアレキサンダー・テクニックに固有の用語を説明し、レッスンの内容を紹介しながら、約320ページに渡って、豊富な経験をもった著者ならではの考察を展開している。その一端は、上記にピックアップした小見出しにもうかがえると思う。
ここでは、アレクサンダー・テクニックの重要な概念のひとつ「inhibition(抑制)」について、紹介してみたい。
これは、姿勢や動作の中から不必要な緊張や過剰な力をなくしていくことである。と書いてしまえば簡単なことだが、なかなか自分では気がつくことができない。
「人間は力を抜くことよりも力を入れることのほうが簡単にできてしまうので、方法に対して冷静ではなく「やる気」だけがあふれている場合、力任せ一辺倒になりやすい。そしてその力への依存が動作から滑らかさと余裕を奪い、その事態に戦うべくさらに力を入れるという悪循環を招きやすい」
このような悪循環から逃れるため、あるいは、習慣的または無意識的行為になってしまっている姿勢や動作にアプローチするための方法について、意識を新たにして考えていかなければならない。
ここには、人間の認識に関わる問題がある。著者は「色」の認識を例にして説明する。
「人間の網膜に映る色彩は、そのときの光によって変化する。試しに一枚の色紙を家の中や屋外の色々な場所に持っていって、その色を見てみるとよい。同じ紙の色でも「実際に見えている色」はそのときどきによって違うのがわかるだろう」
我々が「赤」と口にするとき、「実際に見えている色」とは無関係に、「赤」という色のカテゴリーを表す単語を口にしている。ほとんどの場合、コミュニケーション上はそれで充分だ。(微妙なニュアンスの違いが問題になる場合は、もっと詳細に説明するか、色見本を用意して、多くの「赤」の中から所定の色を選択する)
つまり、我々が「実際に見えている色」を「赤」と言うのは、視覚や色覚の働きではなく、認識の仕方である。視覚や色覚そのものとは別の働きである。
動作についても同じことが言える。例えば、「窓を開ける」という行為は、実際には無数の「開ける」行為を含んでいる。バルコニーに出るための大きな窓と換気用の小さな窓では、実際に「窓を開ける」動作はまったくの別物である。しかし、誰かに「窓を開けて」と頼むときに、体の使い方まで指示する必要はない。
同時に、「窓を開ける」という動作について、我々はそれ以上のことを考えなくなってしまう。「窓を開ける」という(行為の)認識の中に、無数の「開ける」行為の差異が隠蔽されてしまう。
また、認識に関する別の問題もある。感覚の繊細さと感覚に対応する身体器官の大きさの違いである。よく知られているように、脳の運動感覚野と呼ばれる領域では、手の領域のほうが胴体の領域より大きい。体性感覚野についても同じことが言える。つまり、手のほうが「繊細」、あるいは、胴体のほうが「鈍い」わけである。
「「間違い」や「錯覚」ではないが、しかし「大きな感覚」を持った部分が決して「大きな力」を持った部分ではないことにも留意しなくてはならない。「感じられる部位」だけで身体を把握したり、動作を完結しようとしすぎると、まさに「小手先で動く」ような、安定感に欠ける無理な「からだの使い方」にも通じてしまう。主体的に「からだ」と向き合おうとするなら、感覚的には饒舌ではない身体部位の声にも耳を澄ますことが、「からだ」全体の安定の鍵になっているのだ」
胴体(体幹部)の感覚が重要なことを理解していても、胴体の情報を活用することは難しい。手から入ってくる情報をもっと抑えなければいけないのかもしれない。極端に言うと、手は動かさないでおくような方法も試してみるべきかもしれない。
「アレクサンダー・レッスンで行う「からだの使い方」の指導は、足し算の考え方で「からだ」を補強するのではなく、無意識に行っている無理や「やりすぎ」にストップをかけていく、いわば引き算なのだ」
本書は、公認資格を有する日本人アレクサンダー教師による初めての出版物である。今までは翻訳書しかなかったアレクサンダー・テクニックに関して、日本社会の現状をふまえた議論ができるようになったことの意義は大きいだろう。2004.5.16.
補足:
アレクサンダー・テクニックで特筆すべき点は、教師の養成システムが早くからできあがっていたことにある。
アレクサンダー教師の養成は1930年(第2次世界大戦開始の9年前)から始められ、著者が卒業したACAT(The American Center for the Alexander Technique、略称:エーキャット)は、1964年に創設された。アレクサンダーの教え子たちはそうした学校をいくつも設立している。
おまけ:
もし、この本を読む気になったとしたら、次の順番で読むことをお勧めしたい。
まず、「1 アレクサンダー・テクニックとは」を読み、本書後半の「レッスン・ケース」と「よくある質問について」を読む。それから前に戻り、2章以降を読んでゆく。
つまり、レッスンの効果に関する具体的な情報を頭に入れておいてから、2章以降を読んだほうが、わかりやすいと思う。お試しを。

『アレクサンダー・テクニックの使い方』
- 著 者:
- 芳野 香
- 出版社:
- 誠信書房
- 定 価:
- 2,940円(税込)
「これまで、自分の身体や行動に問題が起こるのは「何か(練習や、体力や、筋力や、根性、などなど)が足りないから」と考え、「できないから、しなくちゃ」という方針で改善策を打ち出し続けてきた人には意外かもしれないが、「できない」という人はたいてい「やりすぎている」ことが多い。(中略)習慣性の問題は、本人が具体的な自覚のないままに、一部分に集中しすぎ、恒常的に過剰な力を使っているためにバランスを崩すことで生じることが多い。しかし、そうした状況が長期化するほどに、「何がやりすぎなのか」はきわめて本人に自覚されにくくなっている」
(「1 アレクサンダー・テクニックとは」より)