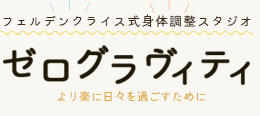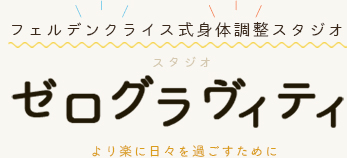『心は孤独な数学者 』 

(数式はいっさい出てこないので、数学がお嫌いでも、どうぞしばらくお付き合いください)
著者の藤原正彦はケンブリッジで教鞭を執ったこともある数学者であり、日本エッセイスト・クラブ賞を受賞(『若き数学者のアメリカ』)しているエッセイストでもある。
「数学上の業績を通して、以前から憧れていた三人の天才数学者がいる。イギリスのニュートン、アイルランドのハミルトン、インドのラマヌジャンである」
本書には、著者にとって「神様のような存在」である3人の数学者について語られた3編のエッセイが収められている。
「神の声を求めて」 アイザック・ニュートン
「アイルランドの悲劇と栄光」 ウィリアム・ロウアン・ハミルトン
「インドの事務員からの手紙」 シュリニヴァーサ・ラマヌジャン
ニュートン以外の二人を知っている読者は少ないだろう。しかし、ニュートンについて何を知っているかと問われれば、林檎(リンゴ)が落ちるのを見て万有引力を発見した人、といった程度の知識にとどまる場合がほとんどかと思う。
ハミルトン(1805年~1865年)は、光学理論や解析力学に貢献し、四元数という「革命的な代数系」を発見し、その後の多くの新しい代数系発見を導いた。
ラマヌジャン(1887年~1920年)は、数学は独力で学んだにもかかわらず、生涯で3000を超える定理・公式を発見した天才で、そのかけ離れた独創性ゆえに、未だに業績の全容が解明されていないという。
著者は、イギリスへ、アイルランドへ、そしてインドへと実際に足を運び、彼らが生活した場所を訪れ、彼らが見た景色をその目で見た。
ニュートン(1642年~1727年)が生まれ育った時代、イギリスは清教徒革命から名誉革命、王政復古へと進む、歴史上の転換期にあたっていた。
ニュートンが生まれた時、父親はすでにこの世になく、ニュートンが3歳の時には母親が家を出て行く。隣村の司祭と再婚するためだった。ニュートンは祖母のもとに残された。
「幼いニュートンは、ほんの二キロ余りしか離れていない教会に住む母親を思慕し続けた。義父はニュートンが母親に会いに来るのを喜ばず、会えば亡き父親を文盲の意気地なしと悪しざまに言うのだった。(中略)
十歳の時に義父が死んだため、母親はウールズソープ村に戻ったが、三人の異父弟妹を連れてのことであり、ニュートンが愛情を独占することはできなかった」
ニュートンは18歳でトリニティ・コレッジに入学する。当時のケンブリッジ大学は聖職者養成を主目的としており、主たる教育は神学、古典学、法律学、医学などであり、数学や科学はまだカリキュラムになかった。
ニュートンが2年生の時、篤志家の基金によってケンブリッジで初めての数学講座が創設され、当時の一流数学者アイザック・バローが初代教授として赴任する。ニュートンは、デカルトやガリレイ、ケプラーなどの著作を読むようになる。
「大学を卒業した一六六五年の夏、大学が臨時閉鎖された。前年からロンドンで猛威をふるっていたペストが、首都の人口の五分の一を殺した後、ついに八十キロ隔てたケンブリッジに届いたのである」
ニュートンはウールズソープ村の実家に帰る。そして、この一年半余の滞在の間に、ニュートンは「微分や積分の核心にほぼ到達」し、力学の基礎を解明し、赤色光や青色光の混じったものが白色光であることを発見した。ただし、これらの理論が公に発表されるのは20年以上も後のことになる。
ケンブリッジに戻り、教授となったニュートンは錬金術と聖書研究に没頭するようになった。
そんなニュートンに転機が訪れる。ハレー彗星の発見者ハレーがケンブリッジにニュートンを訪ねてくるのである。
ハレーはニュートンに問う。「引力が距離の二乗に反比例する時、惑星の軌道はどうなるでしょうか」
ニュートンは即答する。「楕円だ」
ハレー「何故でしょうか」
ニュートン「前に計算したことがある」
ハレー「計算を見せていただけないでしょうか」
ニュートン「新しく書いて送るよ」
「ハレーの質問に対しては、三ヶ月後に、手紙というより論文ほどの厚さのものを送る。質問に答えるだけでなくケプラーの第三法則まで証明してしまう」
ニュートンの勢いはそれで止まらなかった。2年間にわたって「力学と天文学を一つの体系にするという壮大な研究テーマに全精力を注入」した。講義時間以外は部屋に閉じこもり、レクリエーションもとらず、食事さえしばしば忘れるほど研究に集中する。この当時、ニュートンに5年間ほど使えた秘書は、ニュートンが笑うところを一度しか見なかったという。そして、、、
「一年半後の一六八六年、「自然哲学の数学的原理」(通称プリンピキア)は完成し、王立協会に提出された。原稿を見たハレーが、「興奮のあまり死んでしまわなかったのはまさに幸運」と言ったほどの内容だった。(中略)
自然科学の歴史において、『プリンピキア』の出現ほど重大な事件は他にない。アリストテレス、プトレマイオス、コペルニクス、ガリレイ、ケプラー、デカルトと、人類の築き上げてきた力学、物理学、天文学が一変したからである。(中略)
人々にとっては、一六八七年のある日突然、宇宙が変わってしまった。天と地が、数学により一体化したのである」
著者は、『プリンピキア』の出版を「キリスト教の勝利」だと見る。ニュートンの研究は、宇宙の仕組みの中に神の声が美しい調和として存在するに違いないという強い信念に支えられていた。日本の和算家たちは数学的には近いレベルまで達していたが、『プリンピキア』だけは「何百年かかってもとうてい」発見し得なかっただろうと言う。同感である。
「幼少のニュートンにとって、母の愛への渇きを癒すものは、神の声だけだった。長じても、家族や心からの友人に恵まれなかった彼の孤独を癒したのは、神の声だけだったのだろう」
現代の日本に生きる我々は、自然科学と宗教を相容れないものと考えやすい。ニュートンにとっては自然科学と信仰はいずれも「哲学」の範疇に含まれるものだったのだろう。
実は、ニュートンだけでなく、他の二人の数学者ハミルトンもラマヌジャンも神への信仰に生きた人たちだった。ハミルトンはキリスト教徒、ラマヌジャンはヒンドゥー教徒である。
神への信仰が「稀有の力の源泉」となる、こうしたことはただの昔話ではない。現在の中東で起こっていることを見れば、信仰が力になるという事実を認めざるを得ない。近年のマスコミの論調は「信仰≒狂気」といったニュアンスが強いが、「信じること」の力を軽視していると、何か大切なものを見失うことになりはしないだろうか。
ここでは、ニュートンについてだけ紹介したが、本書の半分以上は「インドの事務員からの手紙」(ラマヌジャン)が占めている。
孤高の天才ラマヌジャンについて、インド文化について、ヒンドゥー教について、カースト制について、多くを知ることができる。
面白いことは保証する。
2004.7.11.
補足1:
ハミルトンは「五歳までに、英語、ラテン語、ギリシア語、ヘブライ語を読解」できるようになったという神童だった。「十歳までにはこれにイタリア語、フランス語、ドイツ語、アラビア語、サンスクリット語、ペルシア語が加わる」
ハミルトンは家庭の事情で叔父に育てられるのだが、この叔父の指導により、体を鍛えることも怠らなかった。
大学に入ってからはあらゆる試験で一番をとり、社交界の寵児となる。
「中背ながら、水泳や体操で鍛えた広く厚い胸、聡明に輝く青い目、陽気な笑いと素早いウィット、ハミルトンはハイティーンながら、社交界の引っ張りだことなった」
補足2:
ラマヌジャンは間違いなくノーベル賞級の天才数学者だが、アジア初のノーベル賞受賞者は、ラマンという物理学者(ラマン効果を発見)で、ラマヌジャンと同じく南インドの出身である(生まれはラマヌジャンより1年後)。
また、「二十世紀を代表する天体物理学者で、ブラックホール理論の提唱によりノーベル賞をもらったチャンドラセカール」は、ラマンの甥で、やはり南インドの出身だという。
なぜ、この地域から偉大な科学者が生まれるのか、、、
著者は、南インドに美しいヒンドゥー寺院が無数にあること、つまり、美的センスを備えた人々(多数の建築家や石工など)が長期にわたって存在したであろうことに思いを馳せる。

『心は孤独な数学者 』
- 著 者:
- 藤原 正彦
- 出版社:
- 新潮社(新潮文庫)
- 定 価:
- 460円(税込)
「イギリス人の保守性を考える時、いつも胸をよぎるのは彼等の独創性である。力学(ニュートン)、電磁気学(マクスウェル)、進化論(ダーウィン)はみなイギリス産である。近代経済学(ケインズ)もビートルズもミニスカートもイギリス産である。ジェットエンジンもコンピュータもイギリス産である。
ケンブリッジ大学は戦後だけで三十人以上のノーベル受賞者を輩出している。古い伝統を尊ぶ精神が、新しい流行や時流に惑わされることを防ぎ、落ち着いて物事の本質を見つめることを可能にしているのかもしれない」
(「神の声を求めて」より)