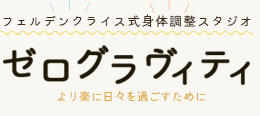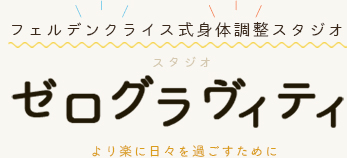『一杯の紅茶の世界史』 

紅茶とコーヒー、今、日本ではどちらが飲まれているのだろう。
紅茶を飲むときには、ほとんどの方はティーバッグを使うと思うが、ポットに茶葉と湯を入れて十分に蒸らしてから飲むなどという手間をかける人は何%くらいいるのだろう。
今や日本のほとんどのレストランでは、食事とセットになった紅茶は、ホットかアイスか、レモンティーかミルクティーかが選べるようになっている。
紅茶の飲み方としては、レモンティーとミルクティーのどちらが優勢なのだろう。
紅茶にうるさいイギリス人は、レモンティーやアイスティーをアメリカ人が考案した邪道な飲み方と考える。しかし、、、
アメリカ人が紅茶を飲むのは間違いなくイギリスの影響だし、アメリカがイギリスから独立するときにはお茶がらみの歴史的大事件があった。
世界史を選択した方は、アメリカの独立戦争に先駆けて、ボストン・ティーパーティ事件があったのを思い出すだろう。
アメリカで消費される茶に対して、イギリスは高額な税金を課していた。そのため、アメリカではオランダやその他の国から茶を密輸するようになり、イギリスの東インド会社は茶が売れなくなり困っていた。そこでイギリス議会は「茶条例」というものを制定し、密輸茶を締め出し、東インド会社の利益を守ろうとした。アメリカでは強力な反対運動が起こった。
1773年、50人ほどのアメリカ人が、ボストン港に入港していた東インド会社の船三艘に積まれていた紅茶をすべて海に捨ててしまう。
この事件の2年後、アメリカ独立戦争が始まる。
「独立戦争以降のアメリカでは、紅茶はイギリスの圧政と束縛の象徴とされ、人々はコーヒーを飲むようになっていた(後略)」
ところで、皆さんがミルクティーを飲むときには、ミルクは後から入れるだろうか(ミルク イン アフター、MIA)。それとも、まずカップにミルクを入れておいて、後から紅茶を注ぐだろうか(ミルク イン ファースト、MIF)。
イギリスでは、この問題が長年(150年以上!)にわたって論じられてきたということをご存知の方は多いと思う。
では、この問題に結論が出されたことはご存知だろうか。
「二〇〇三年、英国王立化学協会が六月二十四日付けのニュース・リリースで、科学的に立証した一杯の「完璧な紅茶のいれ方」を発表した。英国王立化学協会とは、イギリス人だけでなく外国人も含む、科学者、科学教育関係者、化学産業関係者など、四万五〇〇〇人ものメンバーで構成される、世界的な化学研究の団体だ」
結論は、MIFがよい、だった。
詳細な理由は、本書を読んでいただくとして、ミルクが急激に熱くなってしまうMIAは、ミルクが熱によって変性することで風味が悪くなるため、好ましくない、ということらしい。
(こういう議論に大まじめに取り組むユーモア感覚っていいですよね)
本書によれば、今や紅茶の国イギリスでもコーヒー愛好家が増えていて、紅茶の消費量は減っているという。
「アメリカのコーヒー会社によるカフェが、ロンドンをはじめイギリスの各地に出店している」とのことだが、おそらくスターバックスとかそのライバルのことを指しているのだろう。
ヨーロッパで最初に茶に親しむようになったのは、オランダだった。
イギリスはそれにやや遅れ、1657年にロンドンの「コーヒー」ハウスで初めて紅茶が売りに出された。そう、つまり、イギリスにはコーヒーのほうが先に入っていたのだ。
歴史は繰り返す、なのだろうか。
それとも、コーヒーの逆襲が始まったのだろうか。
本書には茶の起源や茶葉の発酵方法による分類(緑茶・白茶・黄茶・青茶・紅茶・黒茶)、製造方法など、基本的な知識もしっかり書かれているし、アールグレイやティーバッグの由来、レモンティーやアイスティーの始まりについても説明されている。
気楽に読める本なので、ぜひ、書店で手にとって見ていただきたい。
2005.10.1.
蛇足:
ある章では、
「コングー(工夫)は、中国では茶の淹れ方にも使われる言葉だが、(後略)」
なんてことも書かれていた。
おまけ:
普豢ア(プーアール)茶の「普豢ア」は、製造方法ではなく地名だが、茶の産地ではない。茶の集積地、つまり茶の市場があるところなのだそうである。
普豢アは、雲南省の南部にあり、ベトナムよりもラオスに近い。ここには、茶馬古道と呼ばれる、石を敷き詰めた古い道があり、かつては中国からチベットへは茶を、チベットから中国へは馬を運んでいた。

『一杯の紅茶の世界史』
- 著 者:
- 磯淵 猛
- 出版社:
- 文藝春秋(文春新書)
- 定 価:
- 714円(税込)
「(17世紀のオランダでは)茶は客が来たときに仰々しくふるまわれた。中国や日本製の、取っ手のない茶碗に注がれ、熱くて持ちにくいので、冷ますために受け皿に少量ずつ移し替え、受け皿から大きな音を立てて飲まれた。これは日本の飲み方を真似たものだ。抹茶の濃茶を飲む時や、渋い煎茶を飲む時に、ずずっと啜って酸素を混じえて飲むとまろやかに甘みを感じることから、取り入れられたのであろう」
(第一章「イギリス人、茶を知る」より)