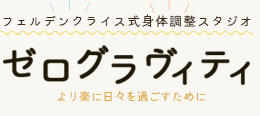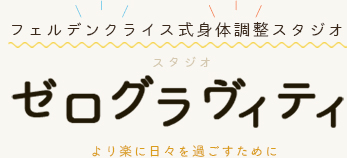『名人伝』 

中島敦という小説家をご存知だろうか。
明治の末頃に生まれ、太平洋戦争のさなか昭和17年(1942年)に33歳で亡くなっている。持病の喘息が悪化したためである。
私は中学か高校の国語の教科書で読んだ『山月記』という短編が印象に残り、その後も何度か読み直した。
あ、『山月記』なら覚えている、虎になった人の話だった、という方は結構いらっしゃるのではないだろうか。
『山月記』はこんな書き出しである。
「隴西(ろうさい)の李徴(りちょう)は博学才穎(さいえい)、天宝の末年、若くして名を虎榜(こぼう)に連ね、ついで江南尉(こうなんい)に補せられたが、性、狷介(けんかい)、自(みずか)ら恃(たの)むところ頗(すこぶる)厚く、賤吏(せんり)に甘んずるを潔(いさぎよ)しとしなかった」
私はこの漢文調の簡潔な文体が大好きなのである。
意味は、「李徴はひじょうに優秀で、若いうちに進士(しんし、昔の中国で国家官僚になるための試験)に合格したが、自信家で協調性がなく、身分の低い役人でいることに我慢がならなかった」といったことで、注釈がなければ到底わからない。
当然、自分では書けないし、現代の作家にもこのような文体は期待できない。
なので、なおさら魅力的に感じるのかもしれない。
その中島敦が弓の「名人」の話を書いたのが、『名人伝』である。
「趙(ちょう)の邯鄲(かんたん)の都に住む紀昌(きしょう)という男が、天下第一の弓の名人になろうと志を立てた。己(おのれ)の師と頼(たの)むべき人物を物色するに、当今弓矢をとっては、名手・飛衛(ひえい)に及(およ)ぶ者があろうとは思われぬ。百歩を隔(へだ)てて柳葉(りゅうよう)を射るに百発百中するという達人だそうである。紀昌は遥々(はるばる) 飛衛をたずねてその門に入った」
百歩離れた柳の葉を的にして外すことがないという弓の名人、飛衛は、入門した紀昌に「眼を瞬いてはいけない」と命じる。
紀昌は家に帰るや妻が動かしている機織り機(はたおり)の下に潜り込み、仰向けになった。眼 とすれすれに機躡(まねき、足で踏む板)が忙しく上下するのをじっと瞬かずに見詰めていようというのである。
二年の厳しい修行の後、紀昌の眼はついに瞬きを忘れた。
「彼の瞼はもはやそれを閉じるべき筋肉の使用法を忘れ果て、夜、熟睡している時でも、紀昌の目はカッと大きく見開かれたままである。ついに、彼の目の睫毛と睫毛との間に小さな一匹の蜘蛛が巣をかけるに及んで、彼はようやく自信を得て、師の飛衛にこれを告げた」
しかし、飛衛は言う。「瞬かなくなっただけでは、まだ、弓は教えられない。次は視ることを訓練せよ。小を視ること大のごとく、微(び)を見ること著(ちょ)のごとくなったならば、戻ってくるがよい」
紀昌は虱(しらみ)を捕らえ、窓に髪の毛でぶら下げる。そして、じっとそれを睨(にら)み続けるのである。毎日毎日、来る日も来る日も紀昌は虱を睨み続ける。
すると紀昌の眼に変化が現れる。虱の姿がわずかずつではあるが大きく見えるようになってきた。紀昌はさらに三年視る修行を続けたところ、とうとう虱が馬の大きさにまでなった。
占めたとばかり紀昌は弓に矢をつがえ虱を射た。
「矢は見事に虱の心の臓を貫いて、しかも虱を繋いだ毛さえ断(き)れぬ。紀昌は早速師の許に赴(おもむ)いてこれを報ずる。飛衛は高蹈(こうとう)して胸を打ち、初めて「出かしたぞ」と褒(ほ)めた。そうして、直ちに射術の奥儀秘伝を剰(あま)すところなく紀昌に授け始めた。
目の基礎訓練に五年もかけた甲斐があって紀昌の腕前の上達は、驚くほど速い」
十日目には百歩離れた柳の葉を百発百中で射ぬくようになった。二十日目には水で満杯になった盃(さかずき)を右ひじの上に載せて剛弓(ごうきゅう)を引いても、こぼれることがない。
一か月の後、百本の矢をもって速射を試みたところ、第一矢が的に当たれば、続いて飛来した第二矢は少しの狂いもなく第一矢の矢筈(やはず)に当たって突き刺さり、更に間髪を入れず第三矢の鏃(やじり)が第二矢の矢筈にガッシと喰い込む。次々と放たれた矢は必ず前の矢の矢筈に喰い込むがために「絶えて地に墜ちることがない」。
「もはや師から学び取るべき何ものも無くなった紀昌は、ある日、ふと良からぬ考えを起した」
自分が天下第一の名人になるためには師の飛衛を殺さなければならない。
密かにその機会をうかがっていたある日、郊外の野原で師の飛衛が向こうから歩いてくるのに出会った。
「とっさに意を決した紀昌が矢を取って狙いをつければ、その気配を察して飛衛もまた弓を執(と)って相応ずる。二人互いに射れば、矢はその度に中道にして相当り、共に地に墜ちた」
互いに射た矢がすべて二人の真ん中で当たった(!)というのだ。
飛衛の矢が尽きたとき、紀昌にはまだ1本の矢が残っていた。紀昌は迷わずその1本を師に向けて放った。飛衛はとっさに傍らの野ばらの枝を折り取り、その刺(トゲ)の先端で矢尻を叩き落とした。
この時に至ってようやく紀昌は我に帰り後悔する。飛衛は危機を脱した安堵感と自らの技量に対する満足感で弟子への憎しみを忘れる。
二人は野原の真中で抱き合って「しばし美しい師弟愛の涙にかきくれた」。
このような師弟の姿を現代の道義観で計るなと作者は言う。美食家の斉(せい)の桓公(かんこう)が己のいまだ味わったことのない珍味を求めた時、厨房の責任者の易牙(えきが)は己が息子を蒸し焼きにしてこれをすすめた。そのような時代の話なのだから、と作者は言うのである。
しかし、さすがに師匠のほうは、このままではいつ殺されるかしれない、と思う。そこでこの「危険な」弟子に新たな目標を提示する。
「爾(なんじ)がもしこれ以上この道の蘊奥(うんおう)を極めたいと望むならば、ゆいて西の方(かた)大行(たいこう)の嶮(けん)に攀(よ)じ、霍山(かくざん)の頂を極めよ。そこには甘蠅(かんよう)老師とて古今を曠(むな)しゅうする斯道(しどう)の大家がおられるはず。老師の技に比べれば、我々の射のごときはほとんど児戯(じぎ)に類する。爾の師と頼むべきは、今は甘蠅師の外にあるまいと」
紀昌は西に向かって旅立つ。
果たして、深い山奥の山頂で紀昌が出会ったのは、よぼよぼの老人だった。
百歳を超えていようかというその背は曲がり、長く真っ白な髭を地面に引きずって歩いている。
結局、紀昌は九年間この甘蠅老師のもとで修行する。
そうして、邯鄲(かんたん)の都に帰ってくるのであるが、、、
(すみません、ここから先は原作でお読みください m(_ _)m)
2010.9.9.
補足:中島敦の作品は青空文庫にも多数収録されている。
青空文庫(ホーム)
中島敦(作品リスト)

『山月記・李陵』
- 著 者:
- 中島 敦
- 出版社:
- 集英社文庫
- 定 価:
- 438円+税
「九年たって山を降りて来た時、人々は紀昌の顔付の変ったのに驚いた。以前の負けず嫌いな精悍な面魂(つらだましい)はどこかに影をひそめ、なんの表情も無い、木偶(でく)のごとく愚者(ぐしゃ)のごとき容貌に変っている。久しぶりに旧師の飛衛を訪ねた時、しかし、飛衛はこの顔付を一見すると感嘆して叫んだ。これでこそ初めて天下の名人だ。我儕(われら)のごとき、足下にも及ぶものでないと」
(「名人伝」 より)