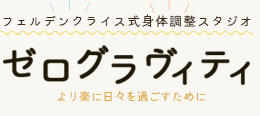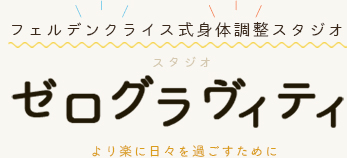『チョコレートの世界史』 

私の職場の引き出しには常にチョコレートが入れてある。コンビニやスーパーで売っている一袋300円弱の安いチョコレートである。
仕事始めのコーヒーを飲む時とか、一息つく時とか、疲れを感じ始めた時とかにチョコレートをつまんで口の中に放り込む。
もちろん、高級品も大好きである。本場ベルギーのプラリネとか、大阪のほうで製造している塩チョコとかたまに食べると本当に幸せな気分になる。
そんな私なので、久しぶりに出かけた神田の三省堂で本書を目にしたとたんに買いたくなってしまった。
まさかその時には、本書で会社組織の福利厚生システム誕生の経緯を知ることになるとは予想もしなかった。
「序章 スイーツ・ロード 旅支度」は、次章以降を読むにあたっての予備知識を頭に入れるための章である。
チョコレートの原料であるカカオ豆の3つの代表的な品種、クリオロ種・フォラステロ種・トリニタリオ種が紹介され、それぞれの産地と味の特徴が説明される。
「カカオは、学名をテオブロマ・カカオ(Theobroma cacao)といい、アオギリ科に属する樹木である。テオブロマは、ギリシャ語で「神(theos)」の「食べ物(broma)」を意味する」
(『チョコレートの世界史』「序章 スイーツ・ロード 旅支度」より)
カカオ豆の採集方法、代表的な産地、産地の歴史的な変遷、カカオ豆を加工してチョコレートにするプロセス、カカオ豆とコーヒー豆の違いなどの説明が続く。
次の「1章 カカオ・ロードの拡大」では、カカオ栽培の起源からマヤ文明・アステカ文明でのカカオ豆の役割(神への供物、貨幣としての使用)、どのような製法で飲用に供していたかなどの説明があり、カカオがスイーツではなく、王侯貴族の薬用飲料であったことがわかる。
アステカ王国がスペインの植民地になると、スペイン人は植民地にしたメキシコでカカオ飲料を飲む習慣を広める。庶民にカカオを売却した利益はスペイン人の懐に収まった。
チョコレートの産地はスペインやフランスの手によって、カリブ海沿岸の各国に広がっていく。
また、この頃にはカリブ海地域でサトウキビが栽培されるようになっていた。「カカオ飲料を砂糖で甘くして、熱くして飲むこと」を広めたのはスペイン人だった。
カカオと砂糖はセットでヨーロッパに受け入れられていったのである。
しかし、この時期のカカオ栽培やサトウキビ栽培には大量の黒人奴隷が従事していた。
「プランテーション経営者は、黒人奴隷が疲労で亡くなるとまた次の奴隷を買い入れた。(中略)新世界のプランテーションで働く労働力を確保するため、アフリカから連れて来られた奴隷は数千万人に及ぶ。新世界からヨーロッパに運ばれた産物は、褐色の肌の人々の涙が産み出したものだった」
(「1章 カカオ・ロードの拡大」より)
チョコレートの歴史にも奴隷貿易が関わっているのである。
「2章 すてきな飲み物ココア」では、16世紀から19世紀にかけてヨーロッパでカカオ飲料がココアとして広まっていくプロセスが記されている。
ココアも紅茶と同じように、始めは王侯貴族や金持ちが健康のために飲用するものだった。ポルトガルには宮廷ココア担当官なる役職が存在した。
19世紀には、オランダのカスパルス・ヴァン・ホーテンの息子がカカオ豆(カカオマス)から油脂を取り除く方法を考案する。
「3章 チョコレートの誕生」では、チョコレートが産業化されていく背景が説明される。保護貿易体制が自由貿易体制に転換し、固形チョコレートが発明され、砂糖の消費が拡大し、スイス人のアンリ・ネスレとその友人がミルク・チョコレートの製造に成功する。アンリ・ネスレは薬剤師で化学の知識があり、このころ乳児用粉ミルクを開発していた。ネスレは粉ミルクをチョコレートの材料に加えることを友人に提案したのだ。
「4章 イギリスのココア・ネットワーク」では、イギリスのチョコレート産業の歴史をたどる。
「十九世紀に技術改良に熱心に取り組み、良質のココアを販売して名を馳せ、イギリスを代表するココア・チョコレート・メーカーに成長していったのが、フライ家、キャドバリー家、ロウントリー家である。この三家はいずれもクエーカー教徒で、親しい間柄だった」
(「4章 イギリスのココア・ネットワーク」より)
イギリスのチョコレートと言われてもピンと来ないかもしれないが、ロウントリー社はあの“キットカット”のオリジナルを製造した会社である。
クエーカーはイギリス発祥のプロテスタントの一宗派で、万人は霊的に平等であるという教義を掲げ、既存の教会の祈祷や典礼方式に対して批判的な態度をとった。1689年の名誉革命で信教の自由が認められるようになるまでは、厳しく弾圧された時期もあった。
19世紀半ばにはクエーカーの企業経営者は産業ブルジョワジーとして頭角を現し始めていた。「クエーカーは信者以外の者との結婚が禁じられていたため、信者間で姻戚関係が結ばれ、緊密なネットワークが形成された」
「ロウントリー社の社長はベンジャミン・シーボーム・ロウントリー(1871~1954)という人物である。社長として実業界に重きをなしただけではなく、ヨークの貧困層に焦点をあてた社会調査を実施し、『貧困-都市生活の研究』という書物を刊行した。国際的にも著名な研究者で、労働者の福祉に関心を持ち、自社工場で試みた福祉プログラムは、イギリスの福祉政策の源流になった」
(「4章 イギリスのココア・ネットワーク」より)
19世紀半ば、産業化・都市化が進展すると、工場労働者が急増し、貧富の差が拡大していた。クエーカーの人たちは、都市部の貧困層に対して何ができるのかと考え、成人学校運動や禁酒運動、動物虐待禁止運動などが展開された。
ロウントリー社があったヨーク市にはスラム化したワーキング・クラスの密集地域があった。貧困調査は11560世帯の各戸に調査員が訪問して、世帯主の職業や賃金、生活状況などを丹念に収集したものだった。これは当時のヨーク市の全世帯の77%をカバーする大調査だった。
「地方都市における貧困状況を解明しただけでなく、家族周期による「貧困のサイクル」という概念を導き出し、子供の幼少期と、親の高齢期に貧困が深刻化することを明らかにした。これは福祉制度の老齢年金や子ども手当の創設につながった」
(「4章 イギリスのココア・ネットワーク」より)
「5章 理想のチョコレート工場」では、ロウントリー社が導入した福祉制度が詳しく説明されている。
ロウントリー社は郊外の新工場の近くに「田園ヴィレッジ」、工場労働者のための住居群を建設した。同時に、理想的なワーキング・クラスのライフスタイル確立のために「コンサートやガーデニングなど文化・スポーツ活動、社会的活動などが展開」された。
老齢年金の制度も設けられた。19世紀の末から働いていた従業員が退職を迎える年齢に達していたためだった。
続いて、遺族年金、疾病給付金、失業給付金といった制度が導入されていった。
ロウントリー社では、工場の生産体制の整備と同時並行して、増大する従業員のための生活保障制度を整えていったのだ。
また、若年の従業員のための教育プログラムを充実させ、働きながら学べるような環境を用意し、早期の離職を無くすようにした。
さらには、ロウントリー社は1919年に週休二日制を採用している。
現代の企業では当たり前の制度がこうして誕生していたとは、それをチョコレートの本で知ることになるとは考えてもいなかった。
こういった制度は、労働運動の末に勝ち取られたものかと勝手にイメージしていたが、そうではなかった。経営トップが従業員のモチベーションの維持(=生活環境の安定化)のために考案したものだった。
21世紀の経営者にも大いに考えてもらいたいものだ。
この後、「6章 戦争とチョコレート」「7章 チョコレートのグローバル・マーケット」「終章 スイーツと社会」と続く。
2011.11.18.
補足1:実は、著者のあとがきには、本書執筆の出発点がこのロウントリー社の膨大な資料を見たことにあると記されている。

『チョコレートの世界史』
- 著 者:
- 武田 尚子
- 出版社:
- 中央公論新社
- 定 価:
- 780円+税
「ゴディバは1926年ブリュッセル創業の家族経営の店だったが、1960年代に、アメリカのキャンベル・スープ社の社長が突然、店を訪ねてきて、店ごと買い取りたいという交渉を始めた」
(「7章 チョコレートのグローバル・マーケット」より)