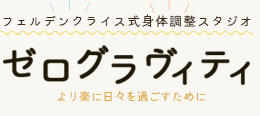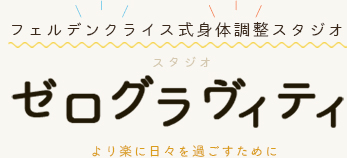37.脳はなにかと 

「意識」の世界よりも「無意識」の世界のほうがずっと大きい。
このような主旨のことを他のページで書いてきました、
稽古雑感ページの「15.「意」とは何か」。
稽古雑感ページの「24.超魔術「姿勢補償」」。
読書遍歴ページの「『マインド・タイム』」。
これについて、もっと身近なことから説明している本がありました。
「目を閉じたままでも、ご飯を口に運ぶことができます。
視界にいつも見えているのに、自分の鼻を邪魔に感じません」
(池谷裕二『脳はなにかと言い訳する』)
ご飯やおかずを箸でつまみ、口の中に入れるまで、どの筋肉をどのくらいの力でどのくらいの時間だけ収縮させるか、そのようなことを意識して計算する人はいません。
顔をどこに向けても鼻先は同じ場所に見えているはずですが、鼻など「見えている気さえ」しません。
どちらも、脳の作用です。筋肉運動に関わる計算は無意識の世界で行われています。視野の中の鼻は無意識に消されているのです。
「日常生活に思いを巡らすとき、もちろん意識にのぼることしか意識できませんから、意識で感知しえたことのみが、あたかも「自分のすべて」であると勘違いしがちです。でも、本当は、無意識の大海原にこそ、脳の真の活動が潜んでいます」
我々が当たり前と思っていることも折に触れて疑ってみることが必要なのです。
例えば、我々が「七色」だと思い込んでいる虹は七色ではありません。光の波長の変化は連続的なものです。七段階に変化しているわけではありません。
「実際、虹を七色とする国は珍しい。イギリスやアメリカでは虹は六色とされているし、フランスや中国では五色、琉球(沖縄)にいたっては二色とかなり少ない。日本でも七色の虹になったのは江戸末期であって、それ以前はここまで細分されていなかった」
こうした虹の色数に類したような思い込みが運動についてもないでしょうか。
とくに大切なことは、「体があって初めて脳が存在する」ということです。
「脳にとっては「体」こそが環境であって、それ以上でもそれ以下でもありません。私たちは、ともすると脳の価値を、体よりも上位に置きがちですが、脳などなくても十分に生きていける原始生物を見ればわかります。体あっての脳なのです」
手があるから、手を動かすための脳の部位ができるということです。
体からの信号がなければ「脳は世界を知り得ない」のです。
ここで、いよいよ野口三千三先生に登場していただきましょう。
「感覚とは自分の「外界に向かっているもの」という強い先入観ができている。私は感覚の本質とするものは、むしろ自分の内側に向かうもの、すなわち内界の情報を受容することにあると思う」
(野口三千三『原初生命体としての人間』より)
脳が世界を知るということは、「内界の情報を受容する」ことなのです。
筋肉にはセンサーがあるということもいくつかのページで書いてきましたが、ここまでの考え方をもとにすると、次のような野口三千三の考え方もわかりやすのではないでしょうか。
「筋肉の働きにとって、大事なことは、量的な力を増すことではないんです。微調整する感覚なんです。質的な違いの分かる感覚が働く筋肉なんです。筋肉は感覚器として、充分働いたときに、初めていい運動器になるんです」
2008.7.27.
(羽鳥操『感覚こそ力』より)

『脳はなにかと言い訳する』
- 著 者:
- 池谷 裕二
- 出版社:
- 祥伝社
- 定 価:
- 1,600円+(税)
「二本足で歩くことで、手をここまで利用できるようになったのは人間だけです。よく考えてみましょう。二本足で歩くようになった動物はほかにもいますね。恐竜図鑑に必ず載っているテラノサウルスは、後ろ足の二本で歩いたり走ったりします。この二足歩行を始めた動物の両手がどうなったか、よく見てみましょう。ほとんど退化しているでしょう。現存の動物では、カンガルーなども似たような変化を遂げつつあります。基本的には、使われない体の部分は退化します。だから二本足で歩くと、手は普通、退化するはずです」
(「12 脳はなにかと体に頼る」より)