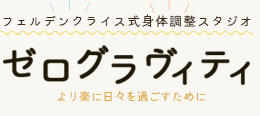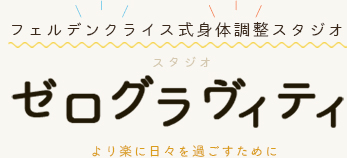『中国近現代史』 

1909年 霍元甲により「上海精武体操学校」が設立される。
1911年 「中華武士会」が設立される(天津)。
1916年 「北京体育講習所」が設立される。講師は楊少侯、楊澄甫、呉鑑泉、孫禄堂など。
1924年 呉公儀は北京から広東に行き、軍の太極拳教官および中山大学体育講師となる。
1926年 陳微明により「至柔拳社」が設立される(上海)。
1928年 南京に「中央国術館」が設立される。
1934年 楊澄甫『太極拳体用全書』が出版される。
そうそうたる武術名家が活躍していた「中国近代」とはどのような時代だったのだろうか。
『中国近現代史』は、いささか古い本だが、アヘン戦争から日清戦争、辛亥革命、抗日戦争、国民党と共産党の内戦、中華人民共和国の成立、文化大革命の終焉までをコンパクトにまとめた良書である。10年ほど前に読んでいたのを半分ほど再読してみた。
再読のきっかけは陳舜臣の『孫文』を読んだことだった。
題名は『孫文』だが、孫文の伝記ではない。孫文(孫逸仙、スン・ヤットセン)が中心にはいるものの、同時代の政治家、軍人、革命家などの活躍や動向についても詳細に書かれている。
『孫文』のほうは、日清戦争が終わった時点から始まり、中華民国南京臨時政府が成立するまでを描いている。
(この本の元の題名は『青山一髪』(せいざんいつぱつ)で、文庫化されるときに『孫文』に改題された。出版社の方針と思われるが、原題よりも購入者を限定してしまうような気がする)
1911年 武昌蜂起、辛亥革命。
1912年 中華民国南京臨時政府が成立、孫文が臨時大総統に就任。
1915年 袁世凱が帝制宣言(翌年 帝制宣言取消、袁世凱死去)。
1919年 ベルサイユ講和会議開始(前年、第一次世界大戦終結)。五四運動。
1921年 孫文、第二次広東政府を組織。中国共産党創立。
1925年 孫文、北京で死去。
1931年 満州事変。
1932年 上海事変。「満州国」成立。
1928年、第二次北伐が完了し、張学良が国民政府(南京、蒋介石)に参加表明することで、中国統一が実現される。
しかし、このときの中国統一は「形の上」だけのことだった。
「財政部長宗子文(そうしぶん)が「中央の財政権はわずかに江西、浙江、安徽、江蘇に及ぶだけで、このうち安徽、江西の収入は中央に入ってこない」(二九年一月)と報告しているように、その他の各省の税収はすべて張学良、閻錫山、馮玉祥、李宗仁、白崇禧、李済深ら地方軍閥が勝手に処分して私兵を養っているありさまだった」
この以前から、近代中国では、中央官僚よりも地方長官のほうが強い権力(軍事力)を保持していた。その最たる人物が李鴻章(りこうしょう)である。
太平天国の乱(1850~1864年)では、太平軍によって南京が占領され、新政府が樹立された。清国正規軍の弱体化は明らかだった。結局、地方で編成された義勇軍が外国軍とともに太平軍を鎮圧したが、このとき李鴻章は江蘇巡撫(じゅんぶ)に任命され、軍を率いていた。
『孫文』の冒頭で李鴻章の言葉が紹介されている。曰く、
「北洋一隅の力を以て(もって)、倭人(わじん)全国の師(軍隊)を搏(う)つ。自(おのず)から逮(およ)ばざるを知る」
その意味は、北洋大臣である李鴻章が個人(一隅)の力で日本(一国)の軍隊と戦った、勝てないことはわかっていた、である。負け惜しみのようにも聞こえるが、日本軍が戦った相手は、清国の軍隊と言うよりも李鴻章の軍隊だった。
清国内には戦争によって李鴻章の影響力が弱まることを期待していた勢力もいたのだ。李鴻章は自分の軍隊が崩壊する前に日本と和睦する道を選んだのである。
日清戦争当時は中国民衆には「抗日」の意識はまだなく、日清戦争の10年後には日本への留学生が急増している。
中国と日本の関係に明らかな亀裂が生じるのは1915年の「二十一ヶ条要求」以後である。
「一九一四年にはじまった第一次世界大戦は、中国をめぐる国際関係を一変させた。英・独・仏・露の各国は欧州戦線に全力を注いでアジアをかえりみる余裕を失い、その間に日本は中国を独占的支配下に置こうと図ったのである」
二十一ヶ条要求を受けた中国では、日本製品ボイコット、愛国貯金(日中開戦に備えて武器購入資金を拠出する)などの運動が展開された。
李鴻章の後継者、袁世凱(えんせいがい)は、日本の要求内容をアメリカに洩らし、「列強の干渉によって日本に譲歩させようと」したが、日本の要求はほとんど認められてしまった。武力を背景にした日本の最後通牒を受けた袁世凱はついに「要求」を受け入れる。
(このような状況にありながら、袁世凱は「中華帝国」の皇帝になろうとする、、、どういう発想なのだろうか?)
中国共産党は創立時から内外に問題を抱えていた。「外」のほうは軍閥との戦い、中でも強大な軍事力を擁する蒋介石との戦いであり、「内」のほうは党内における指導方針の対立であった。
毛沢東の指導権が確立する1942年頃までは、ソ連と繋がりをもつ一派の影響力が無視できず、現実にそぐわない作戦を実施せざるを得ないこともあった。
1934年、コミンテルン(モスクワで結成された国際的な共産主義組織)から派遣された軍事顧問リトロフの指導に従い、共産党軍は国民党軍と正面から対決した。「結果は大失敗」だった。
「紅軍の拠点はつぎつぎに各個撃破されてゆき、三四年三月の広昌陥落以後は、ほとんど回復不能の状態となった」
追い詰められた紅軍は決死の脱出作戦を決行する。史上に名高い「長征」である。
「紅軍は国民党軍の執拗な追撃を振りきり、前方に幾重にも張られた封鎖線をつぎつぎに破り、地方軍閥と戦いながら、十一の省を通過し、十八の山脈(そのうち万年雪をいただく山が五つ)を越え、十七の大河を渡り、六十二の町を攻略しながら、一万二千キロを踏破したのである。犠牲も大きかった。(中略)主力の第一方面軍でいえば、八万六千人のうち陝北にたどり着いたのはわずかに八千人だけであった」
ここに紹介したのは、激動の中国近代史のごく一部だが、多くの武術家が時の流れに翻弄され、思いもよらなかった運命の変転を経験したことだろう。蒋介石とともに台湾に渡った者もいれば、共産党の革命活動に参加して国民党に投獄された者もいる。
『孫文』を読み、さまざまな革命家、活動家の生身のエピソードに接してから『中国近現代史』を読むと、淡々とした事実の羅列が、不思議なほど生き生きとしたイメージで読めた。あえて二冊セットでお勧めする次第である。
(ただ『中国近現代史』にも『孫文』にも武術の話は出てこない。念のため)
2007.2.12.
補足:
清朝は、1888年には当時の最大級の戦艦2隻を中心に強大な海軍力を保持していた。だが、その後清朝は新たな軍艦の購入を取りやめ、海軍経費二千万両で西太后の還暦を祝う「頤和園(いわえん)」を造営した。一方、日清戦争時の日本艦隊は最新の速射砲を装備しており、平均時速も北洋艦隊に優っていた。
以下、『中国近現代史』より、
「この海軍建設費は、主に生糸の輸出によって調達された。それは苛酷な婦人労働によるもので、当時諏訪湖畔の製糸地帯では、「湖水へとびこむ工女のなきがらで諏訪湖が浅くなった」といわれ、また「男は軍人、女は工女、糸を引くのも国のため」という歌が流行していた」
おまけ:
孫文と南方熊楠(みなかたくまぐす)はイギリスで出会い、親友となった。
1892年、南方はイギリスに渡る。大英博物館で図書目録編纂係として勤務していた。この頃、科学雑誌『Nature』に論文を投稿している。
孫文はハワイに住んでいたことがあり、英語は堪能だった。

『中国近現代史』
- 著 者:
- 小島 晋治 + 丸山 松幸
- 出版社:
- 岩波書店(岩波新書)
- 定 価:
- 819円(税込)
「われわれの視点に絶えざる検討を迫るのは、中国の変動だけではない。日本社会の変化に知らず識らず流されてゆく自分自身へのきびしい自己分析を忘れるならば、おそらく正確な中国像を結ぶことは不可能であろう。なぜならこの百五十年の中国の歴史は、近代日本の歩みと表裏をなしているからである。中国近現代史を一貫するものは、時期によってさまざまな表われこそすれ、強烈な民族主義であり、その主要な対象は日本であった。」
(「まえがき」より)

『孫文』上・下
- 著 者:
- 陳 舜臣
- 出版社:
- 中央公論新社(中公文庫)
- 定 価:
- 720円(税込)上下巻とも
「(南方)熊楠は生物学者であり民俗学者であって、とくに菌類のコレクターであったが、神社合祀(ごうし)反対など、反体制的気質が濃厚だった。反体制といえば孫文の気質と共通している。また孫文は医者として細菌学の知識があって、後年、熊楠と会うときは、土産として各地で採集した菌類の見本を持参したものである。」
((上巻)「大英博物館」より)